今日は前から何回か宣伝して来た、10x Genomics ユーザーグループミーティング(東京)のお知らせです!
これ、昨年は10月に行いました。今年は早くも6月28日に東京で行います。
今年は、午前中はサンプル調整・データ解析ワークショップ、午後はお客様の発表、というようにしました。
午前中のワークショップは、基本プレゼンベースです。10xのユーザーを想定しています。10xの前提知識が無いと聞いていてもわからないだろう、と思うからです。
午後のセッションは一般の方(シングルセルに興味のある方)を対象にした、いわゆるユーザーミーティングです。もちろんユーザー以外の方でもウェルカムです。みなさんどんな研究に10xのChromiumを使っているか、興味ありますよね。
-------------------【ユーザーの演者の皆さま】-------------------
Garvan Institute of Medical Research, Laboratory Head, Dr. Alex Swarbrick
Landscape of the Breast Cancer Microenvironment at Single-Cell Resolution
熊本大学ヒトレトロウイルス学共同研究センター, 佐藤 賢文 先生
HTLV-1感染病態解明へ向けた感染者血液のシングルセルトランスクリプトーム解析
富山大学医学部整形外科/Duke University Orthopaedic Surgery, 箭原 康人 先生
scRNA-seqを用いたRNA velocity解析;胎児卵黄嚢 erythro-myeloid progenitor由来破骨細胞は造血幹細胞非依存的に生ずる
東京大学大学院新領域創成科学研究科,鈴木 絢子先生
scATAC-seq/scRNA-seq解析:がん細胞のトランスクリプトーム不均一性解明に向けて
----------------------------------------------------------------------------
ご覧の通り、がんの微小環境、免疫、遺伝子発現、ATAC-Seqなどテーマが多彩に渡ります。また、10xからは、製品アップデート、Spatial、データビューワーの話、さらに当日データ解析ヘルプデスクも設ける予定です。
あと、今回初の試みとして、ライトニングトークセッションを行います。
これは一人5分の発表です。最大6名まで募集します。参加者枠はまだ少しあるので何か発表したい、共同研究者を探したい、という人は是非どうぞ。
ユーザー会が終わった後は情報交換会(という名の懇親会)がありますので是非どうぞ。すべて無料です。何かプレゼント的な、何かがあるかも。
10x Genomics ユーザーグループミーティングの登録はこちら
ちなみに先月行われた台湾でのユーザーグループミーティングは100人以上のお客さんが出席し、大反響でした。
写真は台湾代理店・PharmigeneさんのFBに上がっていますので雰囲気を味わいたい方はのぞいてみてくださいね。世基生物醫學股份有限公司 で検索すればかかってくると思います。
下一站6/28,10x與您相約東京見! 謝謝
10x Genomics のテクノロジーとそのアプリケーションなどを中心にイベントや論文などを時おり紹介するブログ。 「シングルセル解析をもっと身近に!」をモットーに書き綴ります。尚、これは個人的なブログです。会社の意見は反映していません。 Twitterはこちら>https://twitter.com/ken_osaki
2019年6月4日火曜日
シングルセル発現解析の比較 論文その2
前回に続いて、シングルセル解析の比較論文を探していたら良いものを見つけたのでシェアします。Broadのチームが行ったそうです。
前回と名前が似ている論文ですね、こちら
(この話はGenomeWebでも記事になっていますのでこちらもどうぞ)
彼らが比較しているのは以下の7種類のプラットフォームです。
 |
| Ding et al., Fig 1-b |
彼らの定義では、Smart-Seq2とCell-Seq2は低スループット、10xをはじめとするその他Drop-Seq、Seq-Well、inDropsは高スループットとされています。低スループットの方はプレート上で数百の細胞を処理し、高スループットはそれ以外の技術で数千の細胞を処理可能、ということだと思います。この2つはどちらが良いかということではなく、それぞれ長所があると述べています。
彼らの結果のひとつとして、低スループット技術は高スループット技術に比べて検出できた遺伝子数・UMIの数が多かった、というのがありました。ただ、メソッドを読むと、
"We aimed for 50,000 to 100,000 reads per cell for high-throughput methods and 750,000 to 1,000,000 reads per cell for low-throughput methods. "
とあって、ああ、低スループット装置の方は高スループット装置に比べて10倍近く、細胞あたりシークエンス読んでいるんだなと。ここは注意した方が良いです。10xも細胞あたりのリード数を増やしたら、、、もっと遺伝子検出しているはず。しかし処理できる細胞数が数千レベルと多いのでシーケンスコストが高くつきますね。
ここも目的によるのでしょうが、数百の細胞の解析で済む実験と、数千・数万の細胞の解析で得るデータではその実験の規模がだいぶ違います。数万の細胞実験はやはり、シークエンスのコストと精度とのトレードオフが常に問題になるでしょう。
それはさておき、彼らの結果では、高スループット装置の中では、10xのChromiumが一番遺伝子検出感度が高かったそうです。Version 3もちゃんと含まれていて素晴らしい! これは、数千細胞規模の実験をするなら10xのChromiumを使うのが一番良い、ということらしいです。
嬉しい結論。
このようにたくさんの技術をちゃんと比較するには、お金も時間もかかるし大変だと思いますので、Publicな論文があるととても助かりますよね。
今月28日、アキバで10x Genomics ユーザーグループミーティングを行います!
スポンサーも増えました
是非登録の上ご参加ください! 金曜日です プレミアムフライデーです!
2019年5月30日木曜日
シングルセル発現解析の比較 論文
シングルセル装置導入を検討されている方は当然、世にあるたくさんの技術、装置、プロトコルを比較したいでしょう。こういう情報はメーカーよりも第三者の中立な目から判断したものの方が信用しますよね。
そこで最近出たのはこの論文です。
様々な装置がある中で、著者らは現在良く使われている13種類のシングルセル・シングル核のRNA-Seqプロトコル(技術)を使い、同じ条件下で比較しています。同じサンプルを使い、データのフィルタリング条件やダウンサンプリング条件も同じにし、検出遺伝子の感度、クラスタリングの精度などを比較しています。
中立な立場での比較論文はなかなか貴重だと思います。
この中で、Chromiumはどのような位置に評価されているかというと、
クラスタリングの精度では13種類中、上から3番目、だそうです。
ただ、ここで皆さんに注意してもらいたいのは、彼らが実験に使用した試薬は、一世代前のVersion 2だということです。10xではご存知の通り、昨年、3’発現解析用の試薬はVersion 3になり、V2と比較して遺伝子の検出感度が大きく改善しました。
ですので、V3でもう一回やったら、この順位はもしかしたら・・・。
と言ってもキリがないですね。他の会社さんも試薬のバージョンアップしているかもしれませんし。とにかく、一世代前の試薬でも3位というのはすごいと思いました。
フリーの論文(BioRxv)ですし、特にメソッドのところ、解析についてかなり詳しく書いてあるのでオススメです。
オススメなんですが、あえて付け加えるとすると、、、
公平に比較するため、彼らはリードフィルタリングの条件やUMIカウントの条件、生細胞の条件など、解析パイプラインを統一しています。これは良いのかどうか。13種類のプロトコル全体に最適な条件があるとはちょっと思えないので、これはあくまで比較のために同条件で解析した、と考える方が良いのかなと思いました。
あと、ランニングコストについては触れられていません。論文のテーマ上仕方ないですが、これから装置を購入する人にとっては大事な点です。1実験あたりいくらかかるのか? どれだけ手を動かす必要があるのか(実験ワークフローの時間)? サポートは受けられるのか?
そういう点を考慮した上で、さらに1個前のバージョンの試薬でも3位だったことを考えると、今から購入を検討するならもちろん・・・
ところで私たちは6月28日(金)、東京秋葉原で10xユーザーグループミーティングを行います。国際ゲノム会議の翌日です。こちらもぜひ時間が合えばお越しください!
詳しくはこちらを参照ください!
そこで最近出たのはこの論文です。
様々な装置がある中で、著者らは現在良く使われている13種類のシングルセル・シングル核のRNA-Seqプロトコル(技術)を使い、同じ条件下で比較しています。同じサンプルを使い、データのフィルタリング条件やダウンサンプリング条件も同じにし、検出遺伝子の感度、クラスタリングの精度などを比較しています。
中立な立場での比較論文はなかなか貴重だと思います。
 |
| Mereu et al., Fig.1 |
この中で、Chromiumはどのような位置に評価されているかというと、
 | |
|
ただ、ここで皆さんに注意してもらいたいのは、彼らが実験に使用した試薬は、一世代前のVersion 2だということです。10xではご存知の通り、昨年、3’発現解析用の試薬はVersion 3になり、V2と比較して遺伝子の検出感度が大きく改善しました。
ですので、V3でもう一回やったら、この順位はもしかしたら・・・。
と言ってもキリがないですね。他の会社さんも試薬のバージョンアップしているかもしれませんし。とにかく、一世代前の試薬でも3位というのはすごいと思いました。
フリーの論文(BioRxv)ですし、特にメソッドのところ、解析についてかなり詳しく書いてあるのでオススメです。
オススメなんですが、あえて付け加えるとすると、、、
公平に比較するため、彼らはリードフィルタリングの条件やUMIカウントの条件、生細胞の条件など、解析パイプラインを統一しています。これは良いのかどうか。13種類のプロトコル全体に最適な条件があるとはちょっと思えないので、これはあくまで比較のために同条件で解析した、と考える方が良いのかなと思いました。
あと、ランニングコストについては触れられていません。論文のテーマ上仕方ないですが、これから装置を購入する人にとっては大事な点です。1実験あたりいくらかかるのか? どれだけ手を動かす必要があるのか(実験ワークフローの時間)? サポートは受けられるのか?
そういう点を考慮した上で、さらに1個前のバージョンの試薬でも3位だったことを考えると、今から購入を検討するならもちろん・・・
ところで私たちは6月28日(金)、東京秋葉原で10xユーザーグループミーティングを行います。国際ゲノム会議の翌日です。こちらもぜひ時間が合えばお越しください!
詳しくはこちらを参照ください!
2019年4月6日土曜日
Spatial の素晴らしさが8分でわかるビデオ
先週のAACR(アメリカがん学会)に行かれたかたはいますか? 私も何年か前に行きましたがあれは巨大な学会ですよね。
最近の国際学会はウェブで中継するところもあるんですね。AACRも一部無料で公開していますし、一部はYouTubeにも載っています!
日本の学会ではまだ、無いですかねえ。
このリンクには無料でオープンプレナリーセッションが公開されています
私が特にオススメするのは、一番最後にある、
これです。10x Genomics が昨年末に買収した Spatial Transcriptomicsの良いところがコンパクトかつサイエンティフィックにまとまっています。ビデオの長さは8分弱です。
Spatial Transcriptomicsのアプリケーションはまさにこれからのがん研究を加速する、そんな予感がしますね
最近の国際学会はウェブで中継するところもあるんですね。AACRも一部無料で公開していますし、一部はYouTubeにも載っています!
日本の学会ではまだ、無いですかねえ。
このリンクには無料でオープンプレナリーセッションが公開されています
Wrap-up and opportunities for the future
John D Carpten
USC Keck School of Medicine, Los Angeles, CA, United States
これです。10x Genomics が昨年末に買収した Spatial Transcriptomicsの良いところがコンパクトかつサイエンティフィックにまとまっています。ビデオの長さは8分弱です。
Spatial Transcriptomicsのアプリケーションはまさにこれからのがん研究を加速する、そんな予感がしますね
2019年3月30日土曜日
新情報アップデート 10x Genomics
ブログの更新は随分とご無沙汰していました。2019年が始まり、アメリカ企業なのでQ1(1月〜3月)が始まり、日本ではこの時期は年度末。会社として新しい計画が動き出すと共に日本のアカデミアでは締めの季節。
もうすぐ新年度も迎えるタイミングですので、この際新情報をアップデートします
2月のAGBTでも発表されましたが、10xでは今年、3つのアップデートがあります。
ひとつめは「免疫プロファイリングデータベースの公開」
20万ものT細胞をターゲットにして、細胞表面タンパク質の発現、抗原タンパクの特異性、5’側の遺伝子発現、VDJ領域の完全長配列、という種類の情報を一度に、同一細胞から得たデータです。こんな大規模な解析は今までなかったと思います。
これがまもなく公開されます。このようなマルチオミクス解析が、Chromiumを使えば誰でもできるようになったのは、NGSが登場した時の衝撃に似ていると思いません?
二つめは「Spatial Transcriptomics」
これは前回も紹介しましたね。無数のウェルが仕込まれたスライドガラス上に、サンプルの切片を固定し、ウェルの中にあるバーコード付きのオリゴでサンプルのmRNAをキャプチャー、その後NGSで読みます。バーコードは各ウェルの位置情報と対応しているので、後でRNAの発現値と位置情報を結びつけて解析することができる、そんな技術です。
組織のどこに、どんな遺伝子が発現していたのかがわかるわけです。
これももう少ししたら具体的に、アナウンスされる予定です
三つ目は「Chromium Connect」
簡単にいうとオートメーションシステムです。Chromiumが内蔵されたサンプル自動化装置で、細胞混濁液を用意しさえすればあとはエマルジョン化からそのあとのcDNA作製〜NGSライブラリ作製まで自動で行ってくれる装置です。
夕方細胞が用意できた、っていう時もこの装置が夜中働いてくれるので、作業効率を大幅にUPできると思います!
と、ここまでのことでもっと詳細を知りたい方は、こちらから、登録してみてください。
10xから情報アップデートがあったらメールでお知らせが行くようになっています。
登録後にはこれらの説明ビデオも視聴できますよ。ぜひどうぞ!
もうすぐ新年度も迎えるタイミングですので、この際新情報をアップデートします
2月のAGBTでも発表されましたが、10xでは今年、3つのアップデートがあります。
ひとつめは「免疫プロファイリングデータベースの公開」
20万ものT細胞をターゲットにして、細胞表面タンパク質の発現、抗原タンパクの特異性、5’側の遺伝子発現、VDJ領域の完全長配列、という種類の情報を一度に、同一細胞から得たデータです。こんな大規模な解析は今までなかったと思います。
これがまもなく公開されます。このようなマルチオミクス解析が、Chromiumを使えば誰でもできるようになったのは、NGSが登場した時の衝撃に似ていると思いません?
二つめは「Spatial Transcriptomics」
これは前回も紹介しましたね。無数のウェルが仕込まれたスライドガラス上に、サンプルの切片を固定し、ウェルの中にあるバーコード付きのオリゴでサンプルのmRNAをキャプチャー、その後NGSで読みます。バーコードは各ウェルの位置情報と対応しているので、後でRNAの発現値と位置情報を結びつけて解析することができる、そんな技術です。
組織のどこに、どんな遺伝子が発現していたのかがわかるわけです。
これももう少ししたら具体的に、アナウンスされる予定です
三つ目は「Chromium Connect」
簡単にいうとオートメーションシステムです。Chromiumが内蔵されたサンプル自動化装置で、細胞混濁液を用意しさえすればあとはエマルジョン化からそのあとのcDNA作製〜NGSライブラリ作製まで自動で行ってくれる装置です。
夕方細胞が用意できた、っていう時もこの装置が夜中働いてくれるので、作業効率を大幅にUPできると思います!
と、ここまでのことでもっと詳細を知りたい方は、こちらから、登録してみてください。
10xから情報アップデートがあったらメールでお知らせが行くようになっています。
登録後にはこれらの説明ビデオも視聴できますよ。ぜひどうぞ!
2019年1月31日木曜日
Spatial Transcriptomics てどんな技術?
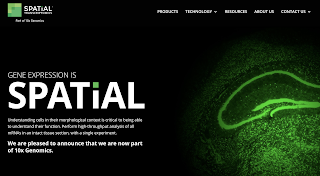 |
| https://spatialtranscriptomics.com/ |
昨年末、10x Genomicsの仲間になったSpatial Transcriptomics
スウェーデンのこの会社、遺伝子の発現量を組織の場所情報と共に得ることで、組織のどの場所でどんな遺伝子が多く発現していたのかを、見ることができるすごい技術を持っているのです。
in situ hybridization ってご存知でしょうか? 私は昔、脳神経化学のラボで実験テクニシャンをやっていたことがあるのですが、その時初めてマウスの脳の切片をin situ hybridization をやったデータを見ました。この技術は遺伝子(メッセンジャーRNA)に対応するプローブを使って、組織切片のどの場所に目的遺伝子が発現していたのかを見ていたわけですが、NGSが出てくるずっと前の当時は最先端の技術でした。その頃マイクロアレイが登場し始めました。
もしin situ hybridization があらかじめ絞り込んだ遺伝子の発現を見る技術だとしたら、Spatial Transcriptomicsの技術は遺伝子を絞り込まずにRNA-Seqを使って網羅的に遺伝子の発現を見ることができます。
ワークフローはWebsiteに説明があります。
イメージとしてはスライドガラスに小さな(直径100μm)ウェルがたくさんあって、そこに切片を固定します。ウェルの底にはウェルごとのバーコード配列がついたキャプチャーオリゴがあって、組織のmRNAはオリゴにくっつきます。
その後cDNA作製からのNGSライブラリ作製へ進み、NGSで読む。読んだ後にデータ解析して、どのウェルバーコード(組織の場所を示す)のどの遺伝子がどれくらい発現していたのか、がわかるわけです。
 |
| https://spatialtranscriptomics.com/workflow/ |
この技術とシングルセルでの応用について、Scienceに「WEBINAR | Mining the transcriptome using spatial transcriptomics: Comprehensive 2D or 3D visualization of all mRNAs in tissue sections」があります。
昨年の6月6日に行われたウェビナーです。超おすすめですよ!
ここから登録するとウェビナーが視聴できます。
今(2019年1月)、Spatial Transcriptomicsは10xの一部です。
このSpace情報とOMICSを繋げて、Spatialomics「スペーシャロミクス」っていうそうです。これから流行るかな?
2018年8月17日金曜日
Chromiumはどんな細胞サイズも多分 OK
前回、Chromiumの特徴をいくつかあげました。
- チップ1つに8サンプル(8チャンネル)流すことができる
- ゲノムDNAなら1ngからスタート(長いDNAにサイズセレクションしていること)
- 細胞なら100個から10,000個までを1チャンネルに流せる
- 細胞のサイズは結構フレキシブル 小さい細胞もOK
- ランした細胞の65%までをキャプチャーできる
- 3’発現解析のフローの場合ラン時間はたったの7分(ゲノムの場合は20分)
このうち、細胞のサイズについて少し付け足します。
細胞、と言ってもその大きさは様々ですよね。
小さいものだと血小板や赤血球は直径数ミクロン(2 μm - 8 μm)
線維芽細胞で10 μm - 15 μm
軟骨細胞で約20 μm
マクロファージはもっと大きくて20 μm - 80 μm
がん細胞株や、神経細胞、肝臓細胞なども大きい
Chromiumのシングルセル技術は、2 μm の細胞も、大きな細胞もキャプチャーすることができます(正確には、シングルセルRNA-Seqの場合は細胞の大きさに制限は無い(修正:とてつもなく大きい細胞の場合、流路を通り抜けることができません。その時は細胞ではなく、核を抽出して流す、というプロトコルがあります。それを使えば細胞の大きさに制限は無い、という意味でした)ですが、シングルセルCNV解析の場合、2018年8月の段階では30μmのサイズまではテスト済み)。
これは他社の技術と違う点です。
様々なサイズの細胞を取りこぼし無く解析できるということは、それだけ正確に組織中で何が起きているかを知ることになるわけです。
もうひとつ、Chromiumの特徴をあげるとすると、
ワークフローが完結する、ということ。
シングルセルを準備するのはユーザーの仕事ですが、そこから先の、
シングルセル内で発現しているRNAや、シングルセルの中に含まれるDNAに、10xのバーコードを付けて、イルミナシークエンサー用のライブラリを作る
まではChromiumがやってくれます。
ゲノムの場合は、ユーザーが高分子DNAを用意し、そこから先は、
DNAフラグメントに10xバーコードを付けて、これまたイルミナシークエンサー用のペアエンドライブラリを作る
までChromiumがやってくれます。
その先のシークエンスはHiSeqなどを使って行ってもらう必要がありますが、出てきたデータの解析は、フリーのLinuxソフトウェアがあります。
コマンドラインになりますが、それほど複雑ではありません。(と言っても全くコマンド使ったこと無い人には敷居は高いかもしれない。実際は、誰かバイオインフォに詳しい人に最初は助けてもらう方が良いと思います)
で、解析後のビューワーは充実しています(シングルセル解析の場合)。
ゲノムアセンブリは大抵、他の技術(例えばPacBioとかHi-Cとか)と組み合わせて解析すると思うので、10人いれば10通りの解析手段があると思うんです。
倍数体とかもバラバラですし。
でもシングルセルの場合は、今までバルク(細胞集団)で行ってきた発現解析やCNV解析などを、1細胞のレベルで解析するということなので、アイデア自体は突飛なことも無いのかなと思うのです。
ただ解析して出てくる結果の解釈が今までと考え方を変えないといけないでしょうね。
これまでバルクでやっていた発現解析は、細胞集団の発現の平均で、異なる組織やタイムポイントなどで比較していたと思います。
それが今度は細胞集団の中でいろんなパターンの発現を示す細胞を見ないといけない。
次元がグッと広がるんです。
付属するビューワーは良くできていて、解析結果をパッと見るフリーツールにしては完成度が高いです。
でもそこからバイオロジカルな答えを導き出すのは、ソフトウェアでは無くて研究者の仕事ですよね。
つくづく、研究者ってすごいなーと思いますよ。こういう業界にいると。
さて、シングルセルといえば、細胞壁のある植物細胞のシングルセル解析は難しいと一般に信じられているかもしれません。
ところが先日とあるユーザーさんが、植物細胞でシングルセル解析をしていることを知りました。
酵素で細胞壁を壊してProtoplastにして、Chromiumに流しているらしい。
まだそれ以上はオープンでありませんが、「結構いける」らしいので、そのうちここでも紹介しますね
登録:
投稿 (Atom)












